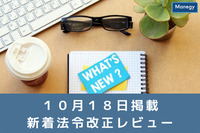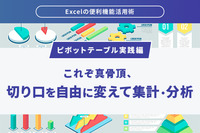公開日 /-create_datetime-/
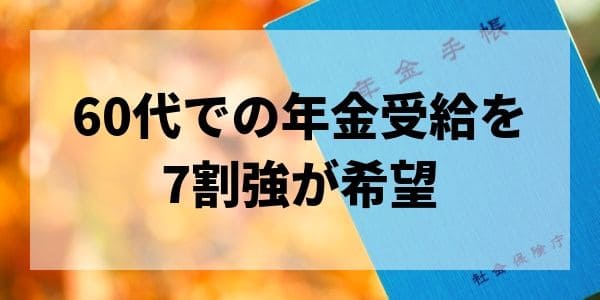
「老後資金は2,000万円不足」するという金融審議会報告書を、麻生財務相が受け取らないという前代未聞の子どもじみた対応で、年金問題がにわかにクローズアップされているが、「年金は本当に大丈夫か」と、サラリーマンの不安は広がっている。
政府は、少子高齢化の対応として、年金の支給開始年齢を現行の60~70歳から引き上げたい意向だ。その対策として、支給開始年齢を自由に選べ、70歳以上を選んだ場合の支給額をアップさせるなどを打ち出しているが、それはどの程度浸透しているのだろうか。
総合旅行プラットフォーム「エアトリ」を運営する株式会社エアトリが、20代~70代の男女1,211名を対象に「公的年金」に関する調査を実施したが、その結果は、政府の思惑とは裏腹に、60~64歳が31.4%、65~69歳が43.0%、70~74歳はわずか16.4%である。
さて、この公的年金の受給開始年齢を繰り下げ繰り上げができることについては、70代は96.1%が知っているものの、20代となるとおよそ3割が「知らない」と答え、若い世代ほど「知らない」が増える結果となっている。
また、受給開始年齢を受給者が自由に選べ、その年齢によって受給額が変わる制度については、「賛成」が46.8%で、「反対」は11.7%である。制度には理解を示すものの、実際に年金をもらうとなれば、「できるだけ早いうちに」というのが庶民の本音といえそうだ。
「反対」の回答は若い世代に多く、「自分たちも本当に年金を受け取れるのか不安だ」や、「定年制度が確立していない中で受給年齢だけ引き上げされることに疑問」という声もある。
年金といえば、高齢者の問題と思いがちだが、実は、年金を支払っている現役世代こそ、真剣に考えなければならない問題である。
ちなみに、一般社団法人公的保険アドバイザー協会が実施している公的保険アドバイザーのセミナー受講者が、累計で10,000名を突破するなど、「老後資金2,000万円不足」問題は、政府が躍起になって火消しに回っているが、一向に鎮火する気配はなさそうだ。
現役ビジネスパーソンの将来に直結する問題だけに、しっかりと見極め、リタイア後の資金計画を早めに立てておく必要がありそうだ。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
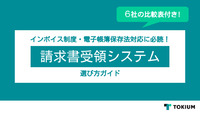
失敗しない請求書受領システム選び方ガイド【2024年1月最新版】
おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -

「人事給与アウトソーシング(BPO)サービス」導⼊事例集【三菱総研DCS】
おすすめ資料 -
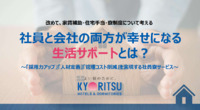
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -
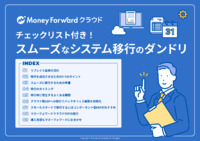
チェックリスト付き! スムーズなシステム移行のダンドリ
おすすめ資料 -
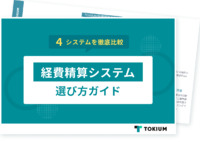
失敗しない!法対応と業務効率化を実現する経費精算システム選び方ガイド【4社の比較表付き】
おすすめ資料 -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース