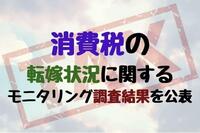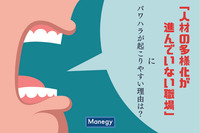公開日 /-create_datetime-/
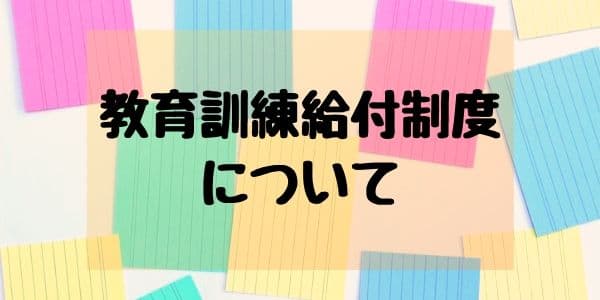
キャリア形成を支援する制度として「教育訓練給付制度」があります。2018年1月には、雇用保険法の一部改正により、制度内容が拡充されました。この記事では、教育訓練給付制度がどんな制度なのか、その基礎に触れていきます。キャリアアップの重要な制度について、学んでいきましょう。
目次【本記事の内容】
教育訓練給付制度は、どんな制度?
教育訓練給付制度は、1998年に誕生した制度です。その後、度々改正が行われてきました。教育訓練給付金とは、教育訓練を受講した際に支払った費用を、雇用保険から一部支給するという制度です。45歳未満の離職者が受講する場合は、基本手当が支給されない期間、受講に伴う諸経費の負担も支援してくれます。
この制度は、雇用の安定と再就職の促進を目的としています。
教育訓練給付制度の種類は2つ
教育訓練給付制度には、2つの種類があります。
1.「一般教育訓練給付金」
厚生労働大臣が指定する講座を受講して修了した場合、その講座(教育訓練施設)に支払った学費の20%、最大10万円が支給される制度です。ただし、講座費用が4,000円を超えなかった場合は支給されません。
一般教育訓練給付金の対象となる講座には、英会話や資格取得のための通信教育、パソコン教室など、さまざまな学びの講座が指定されています。
もし、受講開始前の1年間のうちに、キャリアコンサルタントのコンサルティングを受けていた場合は、その際の費用、最大2万円も支払われます。
2.「専門実践教育訓練給付金」
教育訓練給付金は、2014年に大改正が行われました。そこで創設されたのが、中長期的なキャリア形成をサポートするこの専門実践教育訓練給付金です。
厚生労働大臣が指定する講座を受講している間、または修了した場合、その講座(教育訓練施設)に支払った学費の50%、年間最大40万円が、原則2年、最大3年間支給される制度です。
さらに、修了後、資格取得によって正社員として雇用された場合には、経費の70%、年間最大56万円が支給されます。
対象となるのは、看護師や介護福祉士、保育士や建築士などの資格や、専門学校、専門職大学院などです。一般教育訓練給付金に比べると、比較的取得が難しい国家資格や、長期間技能訓練が必要な美容師や調理師の専門学校など、対象が限られます。
教育訓練給付金の支給対象について
どちらの給付金制度も、雇用保険の被保険者、または被保険者だった人が対象です。それ以外にも、それぞれ給付対象となるには条件があります。
1.「一般教育訓練給付金」
初めて利用する場合には、講座開始日現在で雇用保険加入期間が満1年以上あれば支給の対象となります。受講開始日時点で被保険者でない場合は、被保険者資格を喪失した日から1年以内に受講すれば支給の対象となります。
なお、以前に受給歴のある人は、前回の教育訓練給付金を受給してから3年以上が経過していて、かつ、前回の受講開始日から3年以上の雇用保険加入期間がないと、給付金を支給してもらえません。
2.「専門実践教育訓練給付金」
支給の対象者は、在職中の場合は雇用保険の被保険者で、専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者でなければいけません、初めて利用する場合は、雇用保険加入期間が2年以上、2回目以降の場合は3年以上必要です。
また、受講開始日に被保険者でない人の場合は、被保険者資格を喪失してから受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険加入期間が3年以上、初めて利用する人は2年以上でなければいけません。
教育訓練給付金の支給を受けるための申請方法について
給付金を受けたい場合は申請が必要です。申請方法は、管轄地域のハローワークに相談してみてください。申請手続きは、教育訓練を受けた本人が、受講修了後に申請を行います。
申請時には、それぞれ以下の書類を揃える必要があります。
1.一般教育訓練給付金の場合
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書
・(キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合)キャリアコンサルティングに係る領収書、コンサルティングの記録、キャリアコンサルティングの実施証明書
・本人住所確認書類、マイナンバー確認書類
・雇用保険被保険者証
・教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合)
・返還金明細書(領収書等)
・払渡希望金融機関の通帳、または、キャッシュカード
・教育訓練経費等確認書
2.専門実践教育訓練給付金
・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認表
・訓練前キャリアコンサルティングで1年以内に発行のジョブ・カード、または、「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
・本人・住居所確認書類及び、マイナンバー確認書類
・雇用保険被保険者証
・教育訓練給付適用対象機関延長通知書
・証明写真2枚
・払渡希望金融機関の通帳、または、キャッシュカード
教育訓練給付制度は、申請期間に注意!
給付金を受給するには、申請期間中に申請を済ませる必要があります。
1.一般教育訓練給付金の場合
一般教育訓練給付金を申請するには、受講修了日の翌日からカウントして1ヶ月以内に申請します。
なお原則2ヶ月に1回、教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークにて失業認定を受ける必要があります。
2.専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金の申請は、受講開始から6ヶ月ごとに行わなければいけません。6ヶ月にあたる月の末日の翌日から1ヶ月間に申請をする必要があります(5月が6ヶ月目にあたるなら、6月1日〜6月30日の間)。
追加給付を受ける場合は、訓練を修了後に資格を取得し、一般被保険者として雇用された日の翌日から1ヶ月以内に申請をします。
なお、教育訓練給付制度では、上記の申請期間が過ぎてしまった場合でも、受講修了日の翌日から2年を経過する日までであれば、申請することが可能です。専門実践教育訓練給付金の追加給付の場合も、一般被保険者として雇用された日の翌日から2年を経過する日までは、申請ができます。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。
関連記事:活用したい助成金-起業関連-
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
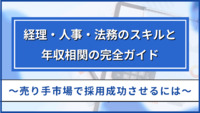
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部が語る!電子署名のメリットと課題を徹底解剖
おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
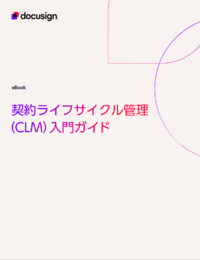
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -

請求書受領サービスの 失敗しない選び方
おすすめ資料 -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -

若手社員の早期離職を防止するためにできること
おすすめ資料 -
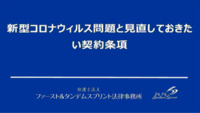
新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

経理は転職サイトを利用すべき?経理人材の転職市場での価値を解説!
ニュース