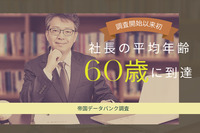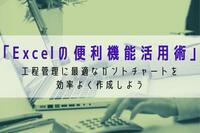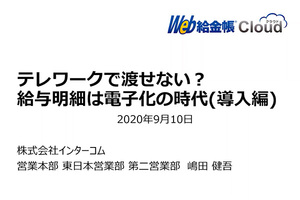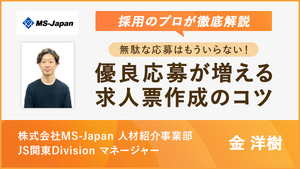公開日 /-create_datetime-/

源泉徴収票は退職者のその年の総収入額と支払った税額を証明する会社が退職者に発行しなければならない書類の一つです。年末調整のときや再就職するときにも必要になります。今回は、退職時に渡す源泉徴収票についての説明と専門家が答えるQ&Aです。
目次【本記事の内容】
源泉徴収票はその年の収入額・税額が記された大切なもの
源泉徴収票とは、会社が支払った給与や賞与などの総支給額と、その総支給額から差し引いた所得税額が記されたものです。
所得税の納税義務は給与所得者本人にあり、本来なら給与所得者が本人で総収入額、必要経費などを差し引いて申告書を作成・提出し、その額に見合う税額を収めるべきです。
しかし、給与所得者が自分で申告書を作成するのは、なかなか大変なことです。そこで、給与支払者である会社が、給与から暫定的に税金を天引きし、会社が本人に代わって納税しています。
もちろん、暫定の数字ですから、税金を払いすぎている場合や、逆に不足することもあります。そこで年末調整を行い、払いすぎている場合には還付、不足している場合は追加で払うようになっていますが、給与所得者にとっては、その年の収入を証明する大切なものです。
所得税額は、その年の収入額が確定してから決まりますから、年の途中で退職した場合は、その年の退職までの期間の収入額と、概算で天引きされている税額を記載した「給与所得の源泉徴収票」を、会社が発行することになっています。
また、会社が発行した源泉徴収票は退職者が転職する場合、転職先の会社に提出の必要があります。発行期限である「退職日の1ヶ月後」までに必ず発行しましょう。
源泉徴収票は「給与所得」と「退職所得」の2種類がある
源泉徴収票は、「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の大きく分けて2種類あります。
「給与所得の源泉徴収票」は、1年間で会社から支払われた給与や賞与の総額と、所得税額や社会保険料額が記載されます。それに対して「退職所得の源泉徴収票」は、退職金が支払われた際に発行し、支払った退職金の額と所得税額が記載されます。退職所得の源泉徴収票を給与所得と別に発行するのは、退職金と給与とでは所得税の計算方法が違うからです。
また、退職金を支払う際には退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらいます。
退職金は、長年の勤務に対する慰労とその後の生活保障の意味合いがあるために、税金が軽減されます。「退職所得の受給に関する申告書」が提出されれば、源泉徴収する際に、退職所得控除を適用することができます。
それに対して「退職所得の受給に関する申告書」が提出されないと、20.42%の源泉徴収をしなければなりません。したがってその場合には、退職者が自分で確定申告を行い、差額の還付を受けなければなりません。
マネジー「教えて専門家」によれば、退職所得の源泉徴収票について、税理士 辻本弘仁氏による以下のようなコメントがあります。
「退職所得の源泉徴収票というものがあります。(ネットで検索できます)
この源泉徴収票には、本人の名前住所マイナンバー、会社の住所名称退職金額、源泉徴収税額、住民税額、入社日退職日等を記入します。
この源泉徴収税額を計算するのが、「退職所得の受給に関する申告書」です。(これもネットで検索できます)
ここに記入しないと、退職金の支給額の2割を源泉徴収しないといけなくなります。退職金をもらった人は、確定申告をしなければならなくなります。
ここに記入すれば、確定申告をする必要がなくなります」
出典:https://www.manegy.com/qa/detail/29
退職所得の源泉徴収票の書き方
退職所得の源泉徴収票の書き方は、「支払を受ける者」と「支払者」のマイナンバー(法人番号)・住所・氏名(名称)などとともに、退職金の支払金額、源泉徴収税額、特別徴収税額(地方税額)などを記載します。記載の方法は、前述した「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合とない場合とで異なります。ある場合には、退職所得控除を適用します。
また、退職金に役員退職手当などが含まれる場合には、「適用」欄に金額や勤続年数、計算の根拠などの記載が必要です。
なお、税務署に提出する源泉徴収票には、退職者のマイナンバーを記載する必要がありますが、退職者に交付するものには、マイナンバーは記載しません。気をつけましょう。
詳しくは、国税庁発行の「令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などに詳しく記載されていますので参照してください。
出典:/news/detail/1376/?url=https%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fpublication%2Fpamph%2Fpdf%2F0020004-166.pdf
専門家に聞く! Q:源泉徴収票について
先月退職した人がいて源泉徴収票を作成したのですが、退職者にお渡しするのは給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)のみで良いのでしょうか。
他に市区町村提出用、給与支払報告書(個人別明細書)、給与所得の源泉徴収票(税務署提出帳)がありますが、合わせて渡した方が良いものはありますか?
また、会社印は押した方が良いのでしょうか。
大変困っています。ご教示お願いいたします。
A:退職者にお渡しするものは...
いつもお世話になっております。
税務のお答えは本来税理士さんが行うべきですが、お急ぎのようですので、回答させていただきます。私社労士ではなく、一人事経験者の回答として、ご理解ください。
①源泉徴収票(受給者交付用):ご退職者ご本人様に交付してください。
②市区町村提出用、③給与支払報告書(個人別明細書):ご退職者の住所地市区町村(退職日時点の)に提出してください。
④給与所得の源泉徴収票(税務署提出用):ご退職者に支払った退職年の給与賞与が250万円「を超える」場合(役員の場合は50万円「を超える」)は、会社所轄の税務署に提出してください。
②・③、④は来年1月31日までに、それぞれ市区町村に給与支払報告書、税務署に(上記に該当する場合は)法定調書とともに、提出してください。
なお、捺印は原則不要ですが、手書きの場合は押したほうがよろしいかと思います。
※④が提出不要の場合は、破棄をしても大丈夫ですが、源泉徴収簿はつけてください。
念のため、国税庁HPの該当ページをリンクしておきますね。
源泉徴収票は退職者・市町村・税務署へ
源泉徴収票は、退職者本人だけではなく、退職者が居住する市町村、会社所在地の管轄税務署にも提出しなければなりません。その年の総収入額によって、住民税や健康保険などの社会保険料、所得税額が決まってくるからです。
また、退職後に新しい会社に勤める場合、新しい会社に源泉徴収票を提出しなければなりません。したがって、経理担当者は、退職した日の1か月以内に、源泉徴収票を作成し、退職者に渡さなければなりません。
源泉徴収票の記載方法、提出方法については、国税庁のサイト(下記)に詳しく載っていますので、参考にするとよいでしょう。
まとめ
従業員の入社・退社には、さまざまな手続きや書類の作成が必要となります。そこには、それぞれルールがあります。人事、経理、総務部門に、それなりの在籍経験があればマスターしていて当然ですが、慣れないと戸惑うことが多くなるものです。そんなときは、ためらわずに「教えて 専門家」を利用しましょう。きっと、あなたが求めている答えにたどりつくことができるはずです
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

若手社員の早期離職を防止するためにできること
おすすめ資料 -

経理BPO業務事例のご紹介
おすすめ資料 -

<人的資本開示 実践編 > 人的資本と組織サーベイ
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -
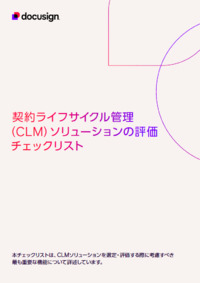
どう選ぶ?契約ライフサイクル管理(CLM)ソリューションの選定に役立つ評価チェックリスト
おすすめ資料 -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -
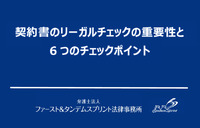
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -
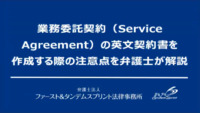
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -
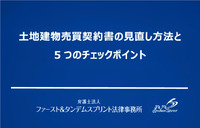
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -
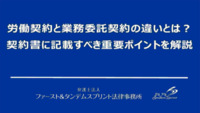
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

経理は転職サイトを利用すべき?経理人材の転職市場での価値を解説!
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース