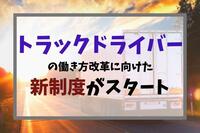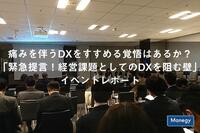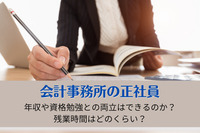公開日 /-create_datetime-/
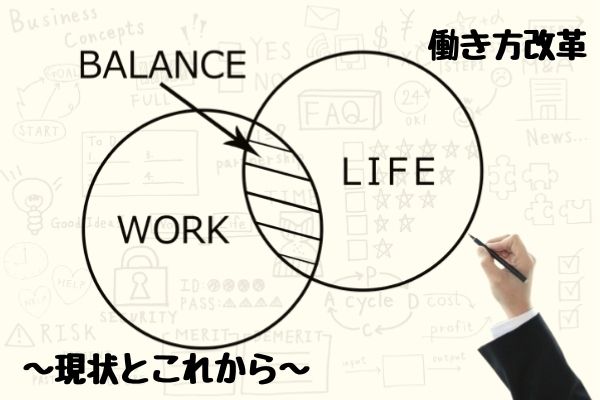
2019年4月に働き方改革関連法案の一部が施行されましたが、今後もさらに新たな法律が施行されていく見込みです。ただ、「働き方改革」という言葉自体は見聞きしているものの、4月の法律施行によって何が変わったのか、今後の法改正で何が変わるのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、働き方改革の現状およびこれからについて解説します。
目次【本記事の内容】
働き方改革とは?
働き方改革とは、各労働者の状況に応じた多様な働き方を選べる社会を実現するために、「労働時間の改善」や「雇用形態に関わらない待遇の公正化」などの措置を講じる制度改正のことです。
近年、長時間労働の常態化により、精神疾患に陥ったり過労死に至ったりするケースが問題となっています。さらに、非正規労働者が不合理な待遇を受けることも多く、制度改正による対応の必要性が生じていました。政府は働き方改革により、残業などによる働き過ぎを防止することで、労働者個々のワーク・ライフ・バランスを実現し、労働者の健康増進につなげるとしています。また、雇用形態に関係なく公正な待遇を確保することにより、正社員とパート・アルバイトなど非正規社員との間にある待遇格差を解消することも、働き方改革における大きな目標とされました。
2019年4月に施行された働き方改革関連法案の内容
一連の働き方改革関連法案のうち、4月1日から導入されたのは労働時間の改善に関する新制度です。これまでは法律によって定められた具体的な上限時間はなく、そのため労働基準法36条に基づいて行われる労使協定(通称:サブロク協定)に「特別条項」が付記されることで、事実上無制限に残業が行われていました。それが働き方改革による制度改正により、年360時間、月45時間が法制度上における上限として規定され、繁忙期などの「特別な事情」があるときでも、月100時間(複数月だと平均80時間)、年720時間を超えてはならないと定められたのです。もし労働者に規定の時間を越えて労働させた場合、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。ただし今年の4月から導入されたのは大企業のみで、中小企業については来年4月からの施行です。
さらに4月から、各企業は有給休暇の日数を年10日以上持っている労働者に、年間最低5日以上を取得させることが義務付けられました。このため各企業は、従業員ごとに有給休暇を漏れなく取得させるために、新たな仕組みを作る必要性も生じています。こちらも違反した場合は6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるので、各企業は確実に有給休暇の付与を行わなければなりません。
ほかにも、高度専門職(年収1,075万円以上の金融商品の開発者やアナリスト、コンサルタントなどの専門職)に対して労働時間ではなく成果に応じた報酬を支払う仕組みを定めた「高度プロフェッショナル制度」も4月からスタートしました。また、終業時間から始業時間の間に一定の休息時間を設けることを定めた「勤務間インターバル制度」(努力義務)や、労働者が産業医に健康相談できる仕組みを整えるよう努めることを定めた「産業医・産業保健機能の強化」に関する制度も、同様に4月から始まっています。
「同一労働同一賃金」の制度が2020年4月から開始
昨年成立した働き方改革関連法では、2020年4月から、正規や非正規などの雇用形態による待遇格差をなくし、「同一労働同一賃金」を実現するための改正法を施行することも決まりました。具体的には「均衡待遇規定」(雇用形態に基づく不合理な待遇差を禁止する)と「均等待遇規定」(雇用形態に基づく差別的な取り扱いを禁止する)が新たな制度として導入され、派遣労働者に対しては「派遣先の労働者との間の均等・均衡待遇」および「一定の要件を満たした労使協定に基づく待遇」が義務化されます。
さらに、2020年4月からは非正規社員が正社員との間に待遇差があると判断される場合は、その内容や理由について事業主に対して説明を求めることができるようになります。また、もし労使で紛争が発生した場合は、都道府県労働局が無料・非公開にて紛争解決手続きを行うことも規定されました。なお、中小企業においては2021年4月から導入されます。
2023年4月には、中小企業における割増賃金率の猶予期間が終了
2010年の労働基準法改正時、月60時間以上の時間外労働に対して5割以上の割増賃金を支払うことが新たに法律で規定されましたが、このとき中小企業は法改正による影響を少なくするため猶予期間が設けられていました。しかし2023年4月にはこの猶予期間が廃止され、中小企業でも月60時間以上の時間外労働を行う場合は、大企業同様の割増賃金を支払うことになります。経営体力のない中小企業の場合、早い段階から業務体制の見直しを行う必要があるでしょう。
まとめ
4月に施行され注目が集まった働き方改革ですが、法制度の施行はこれで終わりではありません。特に来年4月から施行される「同一労働同一賃金」実現のための制度改正は、今年と同様、大きなインパクトを経済界に与えると予想されます。労働者、企業側それぞれが、今後働き方改革がどのように展開されるのかを確認し、働き方や雇用方法を考えておくべきでしょう。
関連記事:働き方改革はどうしてはじまったの?
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
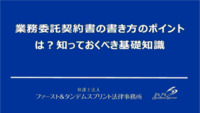
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
おすすめ資料 -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
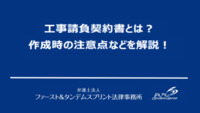
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

「人事給与アウトソーシング(BPO)サービス」導⼊事例集【三菱総研DCS】
おすすめ資料 -
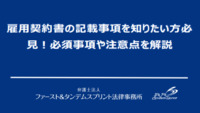
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -
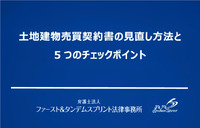
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -
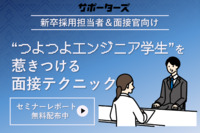
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

経理は転職サイトを利用すべき?経理人材の転職市場での価値を解説!
ニュース