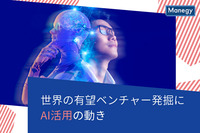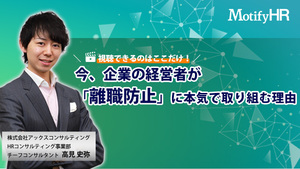公開日 /-create_datetime-/

あなたは退職代行サービスというサービスを知っていますか? 最近では、このサービス事業者から“連絡が来た”という総務部や人事担当者の声を耳にします。
この記事では、この退職代行サービスの内容と実態についてご紹介しましょう。また、「もし、退職代行サービスから連絡がきたらどうすればいいのか」という疑問についても解決します。
目次【本記事の内容】
退職代行サービスとは
退職代行サービスは、本人に代わって退職の意思を伝え“円満退社”させてくれるサービスです。
退職をするには、まず、上司などに退職の意思を口頭で伝えなければいけません。退職届を提出し、退社の期日までは出社する必要があります。退社の日までには事務的な手続きを済ませ、貸与品を返還し、荷物を運び出し……と、様々な作業が待っています。
しかし、この退職代行サービスを利用すると、退職する本人は会社に行くことはおろか、上司や総務担当者とも直接話す必要がありません。なぜなら、連絡のすべては、間に入る弁護士などの業者が代行してくれるからです。
一般的に、退職の意思を伝えると“引き止め”にあうことも多くあります。中には、退職届けを受け取ってもらえない、話を取り合ってすらもらえなかったという事例もゼロではありません。しかし、退職代行サービスを利用すれば、引き止めにあうこともなく、スムーズに会社を辞められます。
退職代行サービス利用の流れ
退職代行サービスの多くは、WEBサイトや電話、LINEから依頼するだけで利用できます。問い合わせのフォームに個人情報を入力したら、雇用形態、契約期間の有無、代行実施希望日を入力。送信するだけで申し込みが完了です。
この退職代行サービスでは、例えば、「即日退社したい」「離職票を送ってもらいたい」など、細かな要望にも対応してくれます。費用を支払ったら細かな打ち合わせをし、代行業務に入ります。あとは、会社からの退職承認の報告を待つだけです。
退職の手続きがスマホ1つで行えるのはもちろんですが、24時間、受付に対応してくれる業者もあり、利便性は増しています。
退職代行サービスのニーズが高まる3つの理由
この退職代行サービスのニーズが高まるのには、大きく3つの理由があります。
1つ目は、「退職の意思を伝えられない」という理由です。退職代行サービスを利用する人の多くは、退職の切り出しにくさを感じています。「これまでお世話になった上司に対して申し訳ない」「水面下で転職を考えていて後ろめたい」「新人だから言い出しにくい」など、面と向かって「会社を辞めたい」の一言がいえないのです。
でも、退職を切り出しにくいからといって、会社を辞めないという選択肢もありません。そこで、他社の力を借りて退職ができる代行サービスへのニーズが高まっているのです。
2つ目は、「ブラック企業を辞めたい」という理由です。ブラック企業の中には、会社を辞めたいと伝えると、「契約違反だ」と脅してきたり、「退職の期日は会社側で決定する」と、悪質な引き止めをしたり、スムーズに辞められないことがあります。中には、退職を告げた途端、パワハラ上司からいじめにあうというケースも少なくありません。
このように、退職の意思を伝えたのになかなか辞められない、不当な処遇を受けるなどのトラブルを避けるために、退職代行サービスが利用されます。
3つ目は、「一瞬たりとも会社に行きたくない」という理由です。退職代行サービスの利用者の中には、精神的に追い詰められていて「会社に近づくことさえできない」という人が少なくありません。退職代行サービスなら、自分の代わりに退職の手続きを行ってくれるので、会社に行く必要がありません。自宅にいながら退職できるのが、大きなメリットです。
退職代行サービス、気になる料金は?
退職代行サービスは、3〜5万円で利用できます。費用は雇用形態などの諸条件によって違うため、事前に業者に見積もりを取るといいでしょう。
代行料金は、銀行振込やクレジットカードで支払うことができます。
“円満”は無理? 実際はトラブルも
「引き止めがないからスムーズに転職できる」「パワハラ上司に顔を合わせる必要がない」など、一見、退職したい人にはメリットの多い退職代行サービスですが、実はトラブルも発生しています。
そのトラブルとは、「逆に会社から訴えられてしまった」「退職できなかった」というものです。“円満退社”できるはずのサービスが、なぜ、このような事態になってしまうのでしょうか。
それは、悪質業者が横行しており、中には弁護士資格を持たない業者が退職代行サービスを行っているケースもあるからです。退職の意思だけを伝えるだけ伝え、それ以外の業務はほとんど行わない(行えない)業者もいます。
そもそも、有給消化や即時退職などの代行業務を行うのは、弁護士らが行う法律事務です。もし、資格のないままに代行業務を行っていれば、それは非弁行為にあたり違法となります。
非弁行為にあたる業者を利用し、会社から訴訟を起こされた場合は、裁判費用や賠償金も負担しなければいけません。「手軽に会社を辞められる」と、安易に業者に頼ってしまうと、このようなトラブルに巻き込まれるきっかけにもなるので、注意が必要です。
退職代行サービス、会社側はどう対処する?
社員が退職代行サービスを利用し、退職を求めてきたら、会社側はどう対処すればいいのでしょうか。
1.社員との契約関係を確認する
まずは、退職代行サービスの業者を社員が本当に利用したのか、委任状や契約書などで確認しましょう。この時点で怪しい点があれば、その業者は無視して構いません。委任状や契約書があれば、退職代行サービスの業者が、弁護士資格を有しているかどうかを確認してください。もし、弁護士資格がなければ、強制力はないため、対応しなくても問題ありません。
2.就業規則や雇用契約を確認する
該当の社員の雇用契約を確認し、就業規則などにも改めて目を通します。通常「退職する場合は、○○ヶ月前までに申し出なければならない」といった就業規則があるため、その期間に則って対処すれば問題ありません。
3.即日退職の理由を確認する
基本的には就業規則に則って対処すれば問題ありませんが、即日退職が可能なケースがあります。それは、以下の5つのケースです。
・パワハラやセクハラなど、ハラスメントを退職理由に挙げている
・賃金未払い
・家族の介護などを理由に就労できない
・本人の病気療養のため就労ができない
・会社が労働関連法令違反をしていて、就業の継続が困難
つまり、「即日退職もやむを得ない」と考えられる場合です。
もし、退職代行サービスの代行業者が「即日退職」を求めてきたら、退職理由を確認し、上記項目に当てはまらないか確認しましょう。
4.退職が決まったら、対応してもらいたい事項を伝える
会社側にも本人に対応してもらいたいことがあるでしょう。退職が決まったら、貸与品の返却など、退職の期日までに対応してもらいたいことを伝えます。もし、業務の引き継ぎが必要であれば、対応してもらいたい旨も伝えてください。
就業規則に引き継ぎの義務が記載されている場合や、引き継ぎの対応をしてもらえない場合は、損害賠償請求をするかどうかも視野に入れて、対応を決めましょう。
5.有給の対応を決める
多くの場合、残っている有給を消化したいと申し出があります。しかし、時季変更権などによって、有給を与えなくてもいいケースもあります。退職日までを有給扱いにするかどうかは、弁護士などと相談しながら、対応していくといいでしょう。
まとめ
自分の会社は、退職代行サービスなど関係がないと思うかもしれません。しかし、社員は、気づかないところで心身の負担を感じ、「退職したいのにできない」と思っているケースもあるのです。「会社を辞めたい」といえないのは、社員側だけに原因があるのではありません。普段から社員が働き続けたいと思う制度づくりや、辞めたい時には気軽に相談できる雰囲気づくりを、会社側も整備していく必要があるでしょう。
関連記事:新入社員の早期退職を防ぐには
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
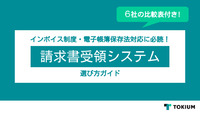
失敗しない請求書受領システム選び方ガイド【2024年1月最新版】
おすすめ資料 -
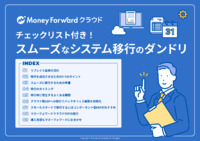
チェックリスト付き! スムーズなシステム移行のダンドリ
おすすめ資料 -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
おすすめ資料 -

働く人の意識を変える定点観測
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -
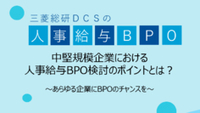
人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)
おすすめ資料 -

経理BPO業務事例のご紹介
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -
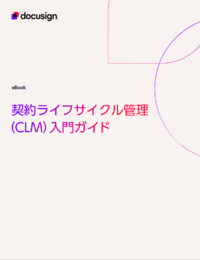
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース