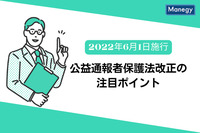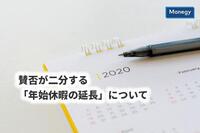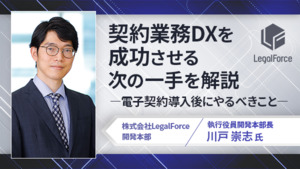公開日 /-create_datetime-/

2019年4月1日より、働き方改革の一環として労働基準法が改正され、年に5日の有給休暇を、企業が時季を指定して従業員に取得させることが義務化されました。
今回は、有給休暇義務化の概要、および有給休暇を消化させるための企業の施策をご紹介します。
目次【本記事の内容】
1. 有給休暇の義務化とは?
a)有給義務化の対象者
b)時季指定の該当者と方法
c)年次有給休暇管理簿の作成
d)就業規則への規定
e)罰則
2.有給休暇を従業員に消化させるための施策は?
a)基準日を統一する
b)有給休暇取得計画表を作成する
c)時季指定の適切なタイミングは?
d)計画年休を導入する
3.まとめ
有給休暇の義務化とは?
2019年4月1日より、年に5日の有給休暇を従業員に取得させることが企業に義務付けられました。
これまでは、有給休暇の取得について企業に義務はありませんでしたが、義務化により、違反した場合には「30万円以下の罰金」とする罰則も設けられました。
まず、有給義務化の概要について見てみましょう。
a)有給義務化の対象者
有給義務化の対象者は、有給休暇が年に10日以上付与される従業員です。
正社員の場合なら、入社から6ヶ月がたち、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日の有給休暇が与えられるので、対象者となります。
アルバイトやパートの場合は、有給休暇は所定労働日数に応じて比例付与されます。週の所定労働日数が4日のケースなら、3年6ヶ月にわたって継続的に勤務すれば、10日の有給休暇が与えられますので、対象者となります。
b)時季指定の該当者と方法
有給休暇の時季指定は、すでに有給休暇を5日以上請求あるいは取得している従業員に対しては、行う必要がありません。それ以外の従業員に対して、企業が時季を指定して5日の有給休暇を取得させます。
ただし、時季を指定する際には、従業員の意見を聞き、できる限り従業員の希望に沿った日に有給が取得できるよう努めなければなりません。
c)年次有給休暇管理簿の作成
企業は、有給休暇の基準日と取得日数、取得した日付を記載した年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
d)就業規則への規定
企業は、有給休暇の時季指定の対象者となる従業員の範囲、および時季指定の方法を、就業規則に記載しなくてはなりません。
e)罰則
年5日の有給休暇を社員に取得させなかった場合、および時季指定について就業規則に記載していなかった場合には、30万円の罰金が課せられます。
有給休暇を従業員に消化させるための施策は?
有給休暇を従業員に消化させるための施策は、どのようなものがあるのでしょうか? 以下に、厚生労働省が推奨する方法について見てみましょう。
a)基準日を統一する
有給休暇の基準日を、年始や年度始めなどに統一することは、有給休暇の管理をしやすくするために有効でしょう。
中途採用などを積極的に行っている企業の場合は、基準日を月初に統一することも、統一的な有給の管理を可能とします。
b)有給休暇取得計画表を作成する
有給をしっかりと消化するには、有給の取得を計画的に行うことが重要です。そのためには、基準日に、従業員ごとに有給休暇取得表を作成するのが良いでしょう。
c)時季指定の適切なタイミングは?
有給の時季指定を行うために適切なタイミングは、従業員のタイプにより2種類に分かれるでしょう。
過去の実績から、有給を比較的順調に取得するタイプの従業員に対しては、基準日から「6ヶ月」などの一定の期間が経過した後、有給の請求・取得日数を確認し、5日未満となっている従業員に対して時季指定を行うのが良いでしょう。
また、過去の実績から、有給を積極的に取ろうとしないタイプの従業員に対しては、年間を通じて計画的に有給を取得できるよう、基準日からできるだけ早い段階で時季指定を行う必要があるでしょう。
d)計画年休を導入する
計画年休を導入することも、従業員が計画的に年休を取得するために有効だと考えられます。計画年休は、従業員にとってもためらいなく有給休暇を取得できることとなります。
計画年休の対象とすることができるのは、有給休暇から5日を引いた残りの日数についてです。
計画年休を付与する際の方式は、次の3種類が考えられます。
・企業全体の休業による一斉付与方式
製造業など、全社または全事業所で操業をストップすることができる企業で活用されている方式です。
・班やグループ別などの交代制付与方式
流通業やサービス業など、定休日を増やすことが難しい企業で活用されています。
・個人別の付与方式
誕生日や結婚記念日など、従業員個人の記念日と合わせて有給を取得する方式も、多くの企業で取り入れられています。
また、班やグループでの交代制、および個人別の付与方式の場合には、次のようにすることで取得率を向上させることができるでしょう。
・夏季や年末年始に付与することで大型連休とする
・ゴールデンウィークなどで休日が飛び石となっている場合に、中日に付与することで連続休暇を実現する
・土日祝日の前後に付与することで連続休暇を実現する
まとめ
休暇を計画的に取得してリラックス出来る時間を持ったり、普段と異なる経験をすることで、仕事にも良い影響があるでしょう。有給休暇は、従業員にとっては心身の疲労回復やリフレッシュに、企業にとっては生産性の向上に役立ちますので、労使双方にメリットがあることです。年5日の義務化を徹底し、従業員がより多くの有給休暇を取得できるための施策に取り組んでいく必要があるでしょう。
また、これまで有給の消化が進んでいなかった企業では、1人の従業員が休んでも業務が回るよう、各部署がチームとして仕事を行い、チーム内での情報共有を密にしていくなどの取り組みも必要となるかもしれません。
関連記事1:年次有給休暇の取得促進に取り組む企業の独自制度
関連記事2:有給休暇制度、日本と外国とはどんなふうに違う?
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
おすすめ資料 -

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド
おすすめ資料 -
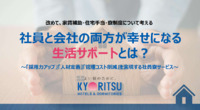
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

働く人の意識を変える定点観測
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -

中堅大企業のための人事給与BPO導入チェックポイント
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース