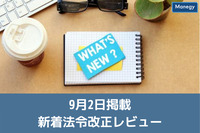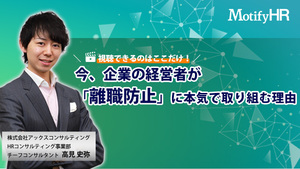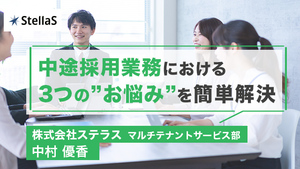公開日 /-create_datetime-/

近年、少子高齢化に伴う労働力人口の減少、ワークライフバランスの重視など価値観の変化により働き方が多様化しています。このような背景から、人材採用手法が多様化しており、これに伴い求職者の求人情報アプローチ手法も多様化しています。このため、ハローワークや求人広告媒体に頼る人材採用手法だけでは、今や自社が必要とする人材獲得が困難な時代になってきています。
目次【本記事の内容】
2. 求人広告の活用
a) 求人広告とは
b) 求人広告活用のメリット
c) 求人広告活用のデメリット
3. 人材紹介の活用
a) 人材紹介とは
b) 人材紹介活用のメリット
c) 人材紹介活用のデメリット
4. ハローワークの活用
a) ハローワークとは
b) ハローワーク活用のメリット
c) ハローワーク活用のデメリット
5. ダイレクトリクルーティングの活用
a) ダイレクトリクルーティングとは
b) ダイレクトリクルーティング活用のメリット
c) ダイレクトリクルーティング活用のデメリット
6. リファラル採用の活用
a) リファラル採用とは
b) リファラル採用活用のメリット
c) リファラル採用活用のデメリット
7. まとめ
採用手法が増加している背景
人材採用手法が多様化している背景として、次の2点が挙げられます。
1.人材不足
人材の売り手市場による母集団形成の困難化、事業スピードの加速、ICT・AI・IoT等の活用による事業構造の変化などにより、旧来の定番的な採用手法では、自社が必要とする人材採用が難しくなっています。
このため、自社の経営課題に対する人的資源充足状況の分析から人材補充計画を立て、計画に適した人材採用手法の使い分けや組合せが重要になっています。
2.働くことへの意識の変化
近年の求職者は収入の安定を重んじる正社員・終身雇用志向の方だけでなく、「自分の趣味・特技を生かしたい」、「やりがいのある仕事をしたい」などライフスタイル充実志向の方も増えてきています。その結果、仕事探しにおいてはハローワークや求人広告媒体の利用ではなく転職フェア、逆求人サイト、人材紹介サービス、友人の紹介・縁故、SNS・インターネットの口コミと、様々な就職チャネルを利用する傾向が強まり、求職者の就職チャネルが多様化しています。
このため、採用マーケティングなどによって求職者の転職行動・指向性を把握し、自社が必要とする人材確保に適切な就職チャネルから適切な情報発信を行い、母集団を形成してゆく必要があります。
人材売り手市場の中でコスト、人材採用の納期厳守、人材採用業務の工数圧縮、現場の人材ニーズ、採用人材の教育・訓練など、山積する人材採用課題に対し、採用手法を限定してしまうことは採用の長期化を招きます。その結果、大学新卒者採用は1人当たり平均50万円、中途採用は同40万円といわれる人材採用コストの更なる上昇を招く要因になってしまいます。
このコスパ面からも採用ミスマッチが少なく、定着率の高い人材を効率的に採用する必要があり、人材採用手法の見直しが重要になっています。
人材採用手法が多様化している現在、おなじみのハローワーク・求人広告媒体以外に自社人材募集サイト、人材紹介サービス、転職フェア、SNSリクルーティングなど、その手法は実に様々です。その中の主要な5手法の特徴、メリット・デメリットなどを比較してみるだけでも、人材採用手法の見直しの重要さが分かるでしょう。
求人広告の活用
求人広告とは
求人広告媒体とは、求人広告専用の媒体のことです。不特定多数の人材募集に適した採用手法といえます。Webサイトを活用する「Web求人広告(転職サイト)」と就職情報誌やフリーペーパーを活用する「紙媒体求人広告」の2種類があります。
<Web求人広告>
転職サイトは全国からいつでもアクセスできるので、転職潜在層を含む幅広い人材からの応募が期待できます。媒体がWebなので掲載できる求人情報量が多く、画像を駆使したビジュアル的な表現が自在にできます。このため広告のデザイン次第で求職者への訴求効果を高めることができ、多くの応募者を獲得し、母集団形成を容易にできる可能性が高まるのが特徴といえます。
広告掲載料は掲載課金型、応募課金型、採用課金型の3コースがあります。いずれのコースも広告の文字数、画像枚数、広告掲載期間、広告掲載順位などにより広告料金が変わります。
<紙媒体求人広告>
紙媒体求人広告には就職情報誌、新聞紙の求人欄、新聞折込みの求人広告チラシ、郵便受け投函や駅構内設置の就職情報フリーペーパーなど様々な形態があります。紙媒体特有の一覧性に富んでいるのが特徴です。
広告掲載料は掲載課金型が一般的。広告掲載枠と広告掲載期間により広告料金が変わります。
求人広告活用のメリット
<Web求人広告のメリット>
(1)全国の転職潜在層を含む幅広い求職者に求人広告ができる
(2)求人の検索軸が多彩なので、採用条件にマッチした求職者の応募が期待できる
(3)掲載できる求人情報量が豊富
(4)社員に自社や職場の魅力や仕事のやりがいを語らせるなど、自社にカスタマイズした求人情報を発信できる
<紙媒体求人広告のメリット>
(1)特定地域の求人広告に向いている
(2)一覧性に富んでいるので転職潜在層の目にも触れやすい
求人広告活用のデメリット
<Web求人広告のデメリット>
(1)面接選考対象者の選別に手間と時間がかかる
(2)不特定多数の求職者を対象にするので、採用ミスマッチの確率が高い
(3)採用条件が厳しいと応募者が少なく、採用コスパが低くなるリスクがある
<紙媒体求人広告のデメリット>
(1)掲載できる情報量が非常に少ない
(2)面接選考対象者の選別に手間と時間がかかる
(3)不特定多数の求職者を対象にするので、採用ミスマッチの確率が高い
(4)採用条件が厳しいと応募者が少なく、採用コスパが悪くなるリスクがある
(5)募集期間が短い(募集期間は日刊、週刊、隔週刊、月刊など媒体の発行形態により異なる)
人材紹介の活用
人材紹介とは
求人企業と求職者の仲介を行う人材紹介サービスは、採用の可能性が高い応募者だけを面接選考できるので、採用ミスマッチのリスクを軽減できるのが特徴です。
人材紹介サービスは「一般紹介型(登録型)」と「サーチ型(ヘッドハンティング型)」に大別できます。
一般紹介型は人材紹介サービス会社が保有する求職者登録者データベースの中から採用条件にマッチした人材を紹介する形態です。人材紹介サービスの大半がこの形態で、単に人材紹介サービスという場合はこの形態を指します。また、この形態には全業種・職種をサービス対象にしている「総合タイプ」と、サービス対象を特定業種・職種に特化した「専門タイプ」に分かれています。
一方、サーチ型は自社保有の求職者登録者データベースはもとより、様々な求職者チャネルを駆使して採用条件にマッチした人材を探し出す形態です。人材採用候補者に対して、面接選考や入社交渉を代行するケースもあります。
人材紹介サービスは急な欠員が生じて人材補充を急ぐ時、事業拡大のために即戦力を必要とする時、専門的人材をピンポイントで獲得したい時などの採用に適しているといわれています。
費用は採用した人材の年収の30―35%が相場。採用した人材が短期で離職した場合は報酬返金規定があるのが一般的です。なお、サーチ型の場合はサービス利用を開始した時点で、成功報酬とは別途に着手金が発生するのが通例です。
人材紹介活用のメリット
(1)採用が決定してから費用を支払う成功報酬型サービスなので、初期費用が不要
(2)求職者と企業の面接日程調整、面接選考の合否連絡など、人材採用活動の多くの業務を人材紹介サービス会社が代行してくれるので、内部コストを軽減できる
(3)採用条件を満たした母集団から人材を選抜できるので求人開始から採用までのリードタイムが短い
(4)非公開で求人できる
人材紹介活用のデメリット
(1)採用人数分の紹介手数料が発生する
(2)採用条件によっては募集期間が長期化する
ハローワークの活用
ハローワークとは
ハローワークとは「公共職業安定所」のことで、厚生労働省の設置・監督に基づき都道府県労働局が地域の総合雇用サービスを提供している地方行政機関です。
主に求職者向けサービスと事業主向けサービスを無料で提供しています。前者は地域の求人情報提供、失業給付等雇用保険手続きなど、後者は求人応募者仲介、雇用保険被保険者資格取得・喪失手続き、雇用促進関連助成金・給付金支給などのサービスを行っています。
ハローワークは外部コストがほとんど発生しない採用手法ですが、求人票作成や選考は自社で行わなければならないので、内部コストが発生します。
ハローワーク活用のメリット
(1)無料で求人できるので外部コストがほとんどかからない
(2)地域内求人をしやすい
ハローワーク活用のデメリット
(1)求人数が多いので自社の求人が埋没しやすい
(2)求人票に掲載できる情報量が限定され、自社の特徴を訴えにくいのでターゲット人材以外の応募者が増加し、その対応で内部コストが上昇するリスクがある
(3)求職者はハローワークへ出向いて受付手続きをし、それから求職票を閲覧し、希望した求人が見つかると求職手続きコーナーで求職手続きをしてと、求人応募手続きに時間がかかる(場合によっては半日)ので、時間的に余裕のある離職者やフリーターなど求職者層が偏っている
ダイレクトリクルーティングの活用
ダイレクトリクルーティングとは
ダイレクトリクルーティングとは、企業側から求職者にピンポイントでアプローチする人材採用手法です。不特定多数の求職者を対象とするハローワークや求人広告媒体と異なり、特定の求職者に企業自らアプローチし、自社が欲しい人材を発掘できるのが特徴です。費用は1人当たり60万円が相場といわれています。
特に専門的な知識・スキルを持つ人材、ゼネラリストや役員となる人材などの採用に効果があるといわれています。
ダイレクトリクルーティング活用のメリット
(1)自社の人材ニーズに適した求職者を面接選考できる確率が高い
(2)自己PRシートなどで絞り込んだ少数の採用候補者から人材を選考できるので、採用ミスマッチを極小化でき、かつ外部コストも圧縮できる
ダイレクトリクルーティング活用のデメリット
(1)ターゲット人材探しから面接選考まで人材採用業務のすべてを社内処理しなければならないので、内部コストが高くなる
(2)採用条件によってはターゲットとなる候補が見つからず募集期間が長期化する
リファラル採用の活用
リファラル採用とは
リファラル採用とは自社の社員に友人・知人を紹介してもらい、自社の人材条件にマッチした人材を採用する手法です。米国ではGoogleやFacebookなど大手IT企業を中心に約85%の企業がリファラル採用を導入しているといわれます。日本ではIT系ベンチャー企業を中心に導入が進んでいるようです。
古くからある縁故採用やコネ採用とリファラル採用の違いは、採用が絶対的であるか相対的であるかの違いにあります。
すなわち、前者は自社役員の縁者、取引先の子弟などが対象になるので、書類選考、面接などの選考プロセスは実質的に存在せず、採用は絶対的であるのが通例です。一方、後者は紹介された応募者を通常の選考プロセスを経て採用します。したがって採用は不可の場合もあり、相対的になります。リファラル採用の費用ですが、人材紹介者への謝礼金が一般的です。採用人材1人当たり20~30万円程度が相場といわれています。
リファラル採用活用のメリット
(1)企業風土、職場環境など自社の特徴を熟知した人が自社に適していそうな人材を紹介するので、他の採用手法と比べると人材採用ミスマッチの確率が低く、定着率が高い
(2) 社員やOBの友人・知人を対象にした求人活動なので、外部コストを安くできる
リファラル採用活用のデメリット
(1)紹介した人材が不採用になった場合、紹介者と被紹介者の人間関係が悪化する可能性がある
(2)社員やOBの友人・知人を対象にした求人活動なので、結果的に思考や労働価値観が類似した人材ばかりが入社してくることになり、人材の多様性がなくなる可能性がある
まとめ
企業が持続的に成長していくためには、優秀な人材の充足が欠かせません。したがって、人材採用は経営戦略の四大要素の1つであるヒト・モノ・カネ・情報からなる経営資源を左右する業務とかねてからいわれおり、「人材採用戦略」や「人材採用マーケティング」が近年は重視されています。
そんな中で人材採用手法の多様化が進んでいます。しかし、本章で取り上げた人材採用手法を見ただけでもそれぞれ一長一短があり、十指に余る手法の中から自社に適した手法を一つだけ選択することは困難であり、また効果的ではないでしょう。
このため、自社に適した手法は選択ではなく使い分けと組合せだといわれています。それぞれの採用方法の特徴をよく理解し、併用する採用手法を検討してて自社にあった採用手法を確立させていってください。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -

<人的資本開示 初級編 > 企業が知っておくべき人的資本と捉え方
おすすめ資料 -
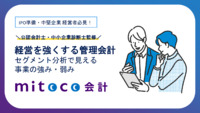
経営を強くする管理会計 セグメント分析で見える事業の強み・弱み
おすすめ資料 -
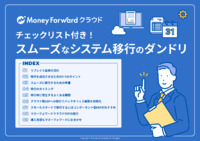
チェックリスト付き! スムーズなシステム移行のダンドリ
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
おすすめ資料 -

経理BPO業務事例のご紹介
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

働く人の意識を変える定点観測
おすすめ資料 -
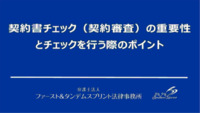
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース