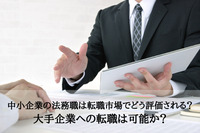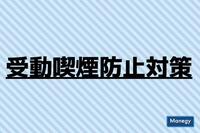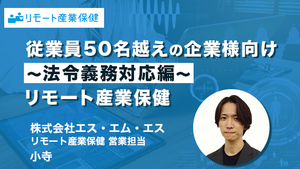公開日 /-create_datetime-/

「新社会人の採用・育成研究会」は、2019年度に入社する新入社員のタイプを、「呼びかけ次第のAIスピーカー型」と名付けたが、今年の新入社員たちの教育は、一筋縄でいかないようである。
「新社会人の採用・育成研究会」のメンバーであり、「若者のトリセツ」などの著者・岩間夏樹氏は、ダイヤモンド編集部のインタビューで、「上司の側からすると、部下としては若干扱いにくい面があるのではないか」と語っている。
その理由は、深刻な人手不足状況の売り手市場で採用された新入社員にとっては、就職そのものを「入ってやった」と、楽観的にとらえていると考えられるからだ。
一方、新人を育成・指導する立場となる先輩社員は、就職氷河期という買い手市場の就職戦線を、血眼になって勝ち抜いてきただけに、「入れていただいた」という意識が強く、会社の都合に合わせ、辛くても本音を隠す会社への忠実さがあったようだ。
「入れていただいた」という意識の上司や先輩世代は、「入ってやった」という意識の今年の新入社員と接する際、どのようなことに気を付けるべきなのか。岩間氏によると、AIスピーカー型の新入社員は、「AIスピーカーと同じで、声をかけないと動かない」そうだ。
AIスピーカーは、音楽をかけることや、天気予報など単純な質問には簡単に答えてくれるが、テレビや照明をつけるには、他の機器の設定や機能追加も必要になり、費用もそれなりにかかるという。
つまり、便利そうなAIスピーカーを使いこなすのはなかなか難しいようで、今年の新入社員も扱いにくい存在であり、どのように向き合えばいいのか、とまどう場面が多くなりそうというのである。
また、経団連会長の “就活ルール廃止”の発表の影響もあり、雇用環境の変化など、終身雇用制や一括採用などの日本型スタイルが変わりつつあることを、敏感に感じ取っているようでもある。
こうした新入社員に「会社の色に染めよう」というスタンスで向き合うと、早期退職につながることも考えられるため、飲み会での芸の強要や、仕事は先輩の背中を見て覚えろといった、一昔前の常識は通用しないと言えそうだ。
また、合理的な理由のない朝礼や朝のラジオ体操などの習慣を押し付けるのも、考え直す必要がありそうで、新人の指導・育成担当者は、上の世代を満足させるためだけに行われてきた会社のよくわからない習慣を、きちんと見直すことも必要になりそうだ。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -
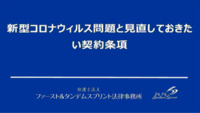
新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -
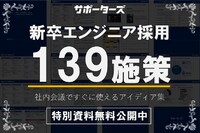
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -
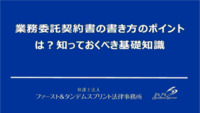
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

中堅大企業のための人事給与BPO導入チェックポイント
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース